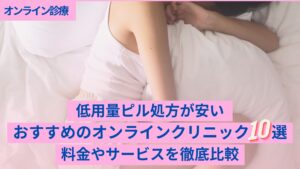「ピルをやめようか迷う…」
「ピルをやめてよかったことを知りたい」
「やめるならいつがいいの?」
上記のように悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
ピルは生理痛をやわらげたり、周期を正常にしてくれる便利な薬ですが、副作用や経済的な負担などを考えると、やめたい気持ちもありますよね。
そこでこの記事では、おもに以下のような内容を解説していきます。
- ピルをやめてよかったと言える理由3つ
- ピルをやめる前に知っておきたいデメリット4つ
- ピルをやめるベストなタイミング3つ
この記事を読むと、ピルをやめるメリットとデメリットがわかります。
この記事の監修者
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 救急科部長
東京大学医学部救急医学 非常勤講師
軍神 正隆(ぐんしん まさたか)
1995年長崎大学医学部卒業。亀田総合病院臨床研修後、東京大学医学部救急医学入局。米国ピッツバーグ大学UPMCメディカルセンター内科、米国カリフォルニア大学UCLAメディカルセンター救急科、米国ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ校公衆衛生学MPH大学院を経て、東京大学医学部救急医学講師。日本救急医学会認定救急科専門医・指導医。2019年より国家公務員共済組合連合会 虎の門病院救急科部長(現職)。
【SNS・関連書籍】
ピルをやめてよかったと言える理由3つ
女性の健康管理や避妊方法として広く利用されている低用量ピル(経口避妊薬)ですが、やめるメリットもあります。
順番に見ていきましょう。
副作用を感じずに済む
ピルの服用中に経験していた副作用から解放される点は大きなメリットになるでしょう。
- 吐き気
- 頭痛
- めまい
などの身体的な不快感が軽減されるだけでなく、
- むくみ
- 体重増加
といった外見的な変化も改善される可能性があるためです。
気分の変動や抑うつといった、精神面での副作用も軽減されるケースもあります。
また長期服用による「血栓症」のリスクも低下するため、より健康に配慮した生活を送れるでしょう。
服用の手間がなくなる
ピルは忘れないように時間を決めて、旅行や出張などのイベント時でも服用する必要があるため、精神的な負担になりがちです。
しかしピルをやめると、毎日決まった時間に薬を飲む必要がなくなり、私生活の手間がひとつ減ります。
また「定期的な通院」「処方箋の更新」などによる、時間的負担が軽減される点もメリットのひとつです。
とくに仕事や学業で忙しい女性にとっては、嬉しいポイントです。
経済的負担が減る
ピルの服用をやめると、経済的負担が軽減されるというメリットも。
低用量ピルを避妊目的で服用する場合は健康保険が適用されず、薬代だけでも1か月あたり「3,000円」程度かかります(※1)。
検診や処方箋の更新にかかる診察料もあわせると、年間で数万円の節約が期待できるでしょう。
これらの費用を自分の趣味や将来への投資に回せる点も、嬉しいポイントです。
ピルをやめる前に知っておきたいデメリット4つ
ピルをやめるメリットはさまざまありますが、もちろんデメリットも存在します。
順番に見ていきましょう。
月経痛や月経不順の再発
ピルには月経痛の軽減や月経不順の改善効果があるため、服用中止によって症状が再発する可能性があります。とくに元々ひどい生理痛や不規則な月経周期に悩んでいた人は、再発によって日常生活に支障をきたす場合もあるでしょう。
また経血量の増加や排卵痛の再発で、仕事や学業への悪影響を与える可能性も考えられます。
「子宮内膜症」「多嚢胞性卵巣症候群」など、婦人科疾患の症状コントロールにピルを使用していた場合、症状の悪化や再燃にも注意が必要です。
避妊率の低下
ピルの副作用中止によって、高い避妊効果が得られなくなります。
代わりの避妊方法としてコンドームの使用があげられますが、ピルと比べて避妊成功率が低い傾向です。
厚生労働省が公表しているデータによると、ピルとコンドームの一般的な使用による避妊率の違いは、以下のとおりです(※2)。
| 避妊法 | 避妊率 |
|---|---|
| ピル | 95% |
| コンドーム | 86% |
コンドームは正しく使用すれば高い避妊率を発揮できますが、破損や装着失敗などのリスクも考慮すると、ピルより心もとない数値です。
そのため、避妊については不安が残ってしまうでしょう。
にきびや肌トラブル
ピルの服用をやめると、ホルモンバランスの乱れによって、にきびや肌荒れが再発する可能性があります。
ピルに含まれるエストロゲンには皮脂分泌を抑制し、肌の状態を安定させる効果があるためです。とくに、もともとホルモンバランスの乱れが原因でにきびなどで悩んでいた場合、症状が再び現れやすい傾向にあります。
またピル服用中に改善していた「肌の乾燥」「毛穴の開き」などが再び現れる可能性も。
肌の状態が安定するまでには時間がかかり、その間はスキンケアの見直しが必要です。
心身の不調
ピルをやめると、ホルモンバランスの変化で心身が不調になる場合もあります。
具体的に身体面では、
- 頭痛
- めまい
- 吐き気
などが生じる場合あります。
精神面では、
- 気分の変動や抑うつ感
- イライラしやすくなる
- 不安感が強くなる
などがあげられます。そのため、一時的に仕事や学業にも悪影響が出るケースもあるのです。
ピルをやめるベストなタイミング3つ
ピルをやめる際は、一時的な体調の乱れや生活への悪影響を与えるリスクを考慮し、以下3つのようなベストタイミングを選ぶことが重要です。
順番に解説していきます。
妊娠を希望するとき
妊活を始める場合、ピルをやめるベストなタイミングは妊活開始の「約3か月前」だといえます。
実際に、研究論文によると、ピルの服用をやめたあと「1~3か月」は生理不順になることが報告されています(※3)。
妊娠確率を上げるためには、生理周期が安定していることが重要な要素のひとつです。
そのため生理を自然な周期に整え、排卵のタイミングを把握することが重要です。
長期休暇や連休の前
可能であれば、仕事や学業の繁忙期を避け、生活にゆとりのある時期を選びましょう。
ピルをやめた際の体調変化に、ゆとりをもって対応しやすいためです。
具体的には、
- 長期休暇に入る前
- 仕事のプロジェクトの区切りがついたとき
があげられます。
とくに服用中止後の数か月間は、月経痛の再発や心身の不調が起こる可能性があります。
そのため十分な休息が取れ、通院できる余裕がある時期を選ぶと、ストレスをおさえてピルをやめられるでしょう。
ピルを使い終えたとき
現在服用しているピルのシートを、最後まで飲み切ったときもピルをやめるベストタイミングだといえます。
シートを最後まで飲み切ったタイミングでピルの服用をやめると、次回の出血時期が予測しやすく、月経周期の乱れを小さく抑えられるためです。
具体的には、21日分のピルを服用し終えたあとの休薬期間(もしくはプラセボ錠服用期間)に入ってから中止すると、自然な形でホルモンバランスを整えられます。
また消退出血の始まりも予測しやすくなるため、生理用品の準備といった事前の対策も立てやすくなるのです。
ピルを中止する選択肢もある
ピルの服用を完全にやめるのではなく、体調や生活環境の変化に応じて、一時的に中止する方法も選択肢のひとつです。
一時中止のメリットとしては、
- 費用負担の軽減
- 副作用がつらい場合の緩和
- 通常時の体調を確認できる
などがあげられます。
ただしピルの服用を中止する際は、医療機関で相談し、適切なタイミングと方法についての指導を受けましょう。
ピルをやめることに関するよくある質問3つ
ピルをやめることについて、よくある3つの質問をまとめました。
順番に見ていきましょう。
ピルやめたあとの基礎体温はいつから測り始めればいい?
ピルの「最終服用日」から測り始めましょう。
自然な生理周期への移行状況や、排卵の有無を把握できるためです。
ピルをやめたあと不妊になる可能性はある?
ピルをやめたあと、不妊になる可能性は低いといえます。
実際に欧州が行った研究結果によると、ピルの服用中止後の1サイクル目で「約20%」が妊娠し、1年後には「80%」が妊娠したと報告されているためです(※4)。
なお妊娠率は、ピルを使用していなかった女性と同程度です。
ピルをやめたあと、体重の変化はある?
個人差や薬の種類による違いはありますが、ピルをやめたあとに体重の変化が現れるケースもあります。
ピルをやめたい理由が副作用ならDMMオンラインクリニックに相談
ピルの服用をやめると、
- 副作用からの解放
- 服薬の手間・経済的負担の軽減
といったメリットがあります。一方ピルの服用をやめた場合、以下のようなデメリットがある点も認識しておきましょう。
- 月経痛や月経不順の再発
- 避妊効果の低下
- 心身の不調
ピルの服用をやめる際は、長期休暇前など生活にゆとりのある時期を選び、現在服用中のシートを使い切るタイミングでの中止をおすすめします。
もし副作用が理由でピルをやめるか迷っているのであれば、オンライン診療サービス「DMMオンラインクリニック」に相談してみてはいかがでしょうか。
医師のアドバイスを受けられるため、あなたにとってベストな選択ができるようになりますよ。
【参考文献】
(※1)北里大学「産婦人科自費料金表」2021年12月1日
(※2)厚生労働省「経口避妊薬(OC)の有効性についてのとりまとめ」
(※3)国立保健医療科学院|京都府立医科大学 産婦人科(岡田弘二,東山秀馨)「経口避妊薬服用後妊娠による心身障害児 発生の防止対策に関する研究」
(※4)PMC|Department of Obstetrics & Gynaecology, University of Cape Town, Rondebosch, South Africa(Athol Kent)「Pregnancy Rates After Oral Contraceptive Use」