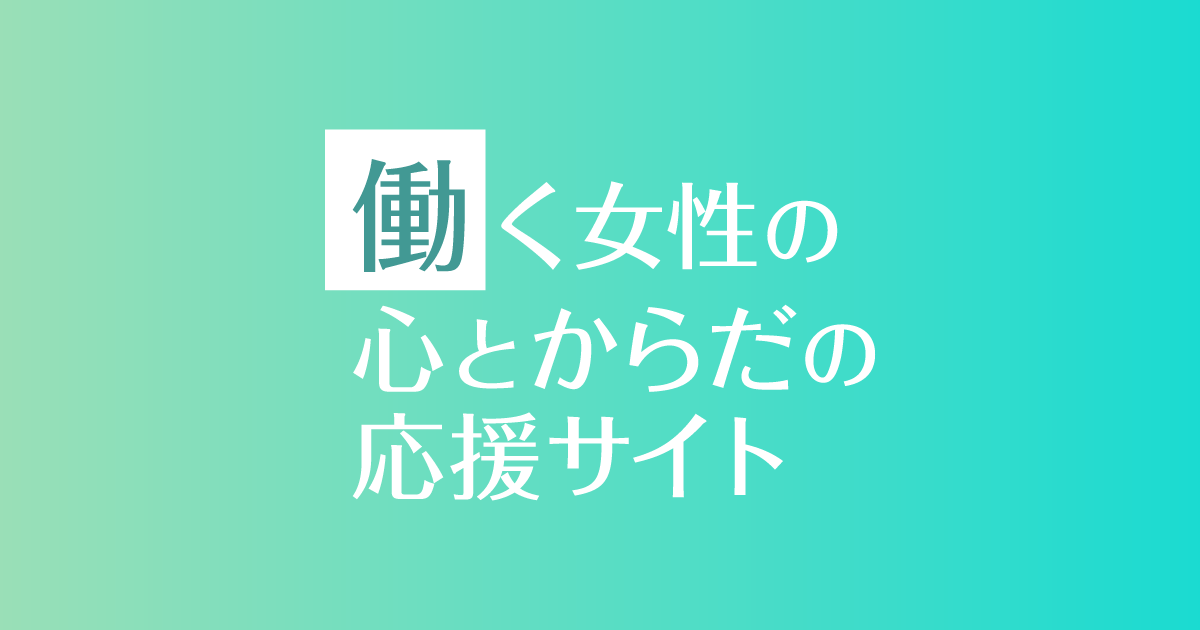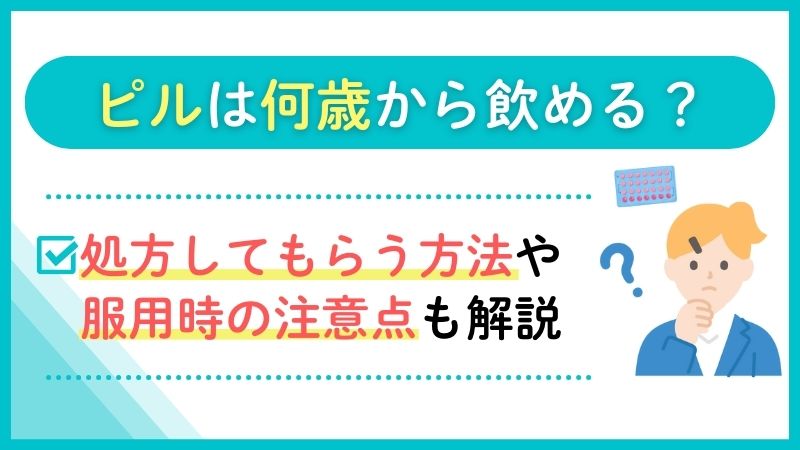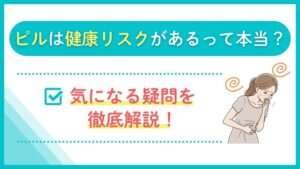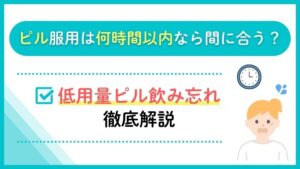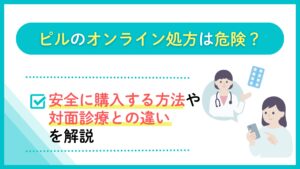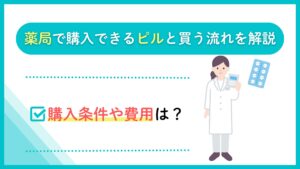ピルは、生理が始まっていれば何歳からでも服用できます。具体的には生理が始まる12歳前後から閉経する50歳頃までが対象です。この記事では、初めてピルを服用する方に向けて、ピルの費用や注意点、処方してもらう方法について解説しています。
「ピルは何歳から飲める?」
「未成年でも親の同伴なしで処方してもらえるの?」
上記のようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ピルは女性ホルモンが配合されている経口避妊薬です。
生理が始まっていれば10代でも服用でき、避妊効果のほか、生理痛を和らげたり月経周期を整えたりする効果が期待できます。
ただし、ピルには副作用のリスクがあり、健康状態によっては服用できない場合もあります。
とはいえ、医師の判断で正しく服用し、副作用について知っていれば、恐れる必要はありません。
本記事では、ピルを服用できる年齢や処方してもらう方法について解説します。
ピルの種類や価格、服用時の注意点についても説明するため、ぜひ参考にしてください。
この記事で解決できるお悩み
この記事の監修者
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 救急科部長
東京大学医学部救急医学 非常勤講師
軍神 正隆(ぐんしん まさたか)
1995年長崎大学医学部卒業。亀田総合病院臨床研修後、東京大学医学部救急医学入局。米国ピッツバーグ大学UPMCメディカルセンター内科、米国カリフォルニア大学UCLAメディカルセンター救急科、米国ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ校公衆衛生学MPH大学院を経て、東京大学医学部救急医学講師。日本救急医学会認定救急科専門医・指導医。2019年より国家公務員共済組合連合会 虎の門病院救急科部長(現職)。
【SNS・関連書籍】
ピルは何歳からでも服用できる
ピルは、閉経を迎える50歳頃までの間、何歳からでも服用できる薬です。
WHO(世界保健機構)が定めているピルの服用基準では、生理が始まっていれば服用できるとされています。
使用目的は避妊のほか、生理痛や経血量の改善、月経周期のコントロールなどです。
ただし、これまでにかかった病気や健康状態によっては、ピルの服用により血栓症や脳卒中などにかかるリスクが高くなる場合があります。
年齢的には問題がなくても、安全に使用できないケースがあるのです。
また、ピルには複数の種類があり、女性ホルモンの配合量や割合が異なります。
安全かつ効果的に使用できる薬を処方してもらうには、医師に健康状態を正しく伝えることが大切です。
ピルの処方に保護者の同意が必要な場合もある
未成年でピルの処方を受けたい場合、医療機関によっては保護者の同伴や同意書が必要な場合があります。
保護者の同意が必要なくても、親にばれたくない方は保険適用かどうかを注意しておくべきです。
保険適用でピルを処方してもらった場合、保険加入者である保護者に医療機関名と医療費の通知が送られます。
自由診療の場合は、保険証を使わないため保護者に通知は届きません。
<未成年がピル処方に関して注意すべきこと>
- 保護者の同意書・同伴が必要か
- 保険適用で処方される場合、保護者の理解を得られるか
- 高校生の場合、処方してもらえるか
また、高校生の場合はそもそもピルの処方を行っていない医療機関もあります。
保護者の同意の有無や高校生へのピル処方は、医療機関によって対応が異なるため、診察を受ける際は、ホームページや電話で確認しておきましょう。
ピルを処方してもらう方法2つ
ピルを安全に服用するには、医師の診察を受ける必要があります。
海外の医薬品購入を代行してくれる個人輸入代行サイトは、安全性が保証されていないため利用するのは危険です。
個人輸入で手に入れたピルによって健康被害が起きても、医療費などの救済が受けられません。
ここでは、安全にピルを処方してもらう2つの方法を解説します。
婦人科で診察を受ける
ピルは、病院やクリニックの婦人科に行って診察を受けると処方してもらえます。
医療機関によっては、健康状態や副作用のリスクを判断するための血液検査が行われる場合もあるでしょう。
過去にかかった病気や検査の結果によっては副作用のリスクが高いと判断され、処方されない場合があります。
内科でもピルの処方を受けられますが、ピルを取り扱っているかどうかは医療機関によって異なります。
受診する前にホームページや電話で確認しておくと安心です。
オンライン診療を利用する
オンライン診療とは、ビデオ通話やチャットで医師とやり取りし、処方が受けられるサービスです。
ピルが処方され、オンライン上で決済すれば自宅に郵送されます。
診療時間内に受診する時間がない方や、婦人科へ行くのは気が引ける方も、隙間時間や移動時間を使って診察を受けられるのです。
ただし、体の状態によっては血液検査やエコー検査が必要になり、対面診療を勧められる場合もあります。
ピルの種類
ピルは、女性ホルモンであるプロゲステロンとエストロゲンが配合された薬です。配合される量によって、主に3つの種類に分けられます。
| ピルの種類 | 主な目的 |
|---|---|
| 低用量ピル | ・避妊 ・月経困難症、子宮内膜症の改善 |
| 中用量ピル | 生理日の移動 |
| アフターピル(緊急避妊薬) | 性行為後の避妊 |
効果や使用場面について、それぞれ解説します。
低用量ピル
低用量ピルは、少量のプロゲステロンとエストロゲンを服用することで排卵を防ぐ薬です。
21日間服用したあとに7日間の休薬期間があり、この期間に出血が起こります。
ピルの種類によっては、服用習慣を崩さないために、ホルモン剤が含まれていない偽薬を7日間内服する製品もあります。
低用量ピルの服用で期待される効果は、以下のとおりです。
- 避妊
- 生理痛の改善
- 過多月経の改善(生理時の出血量が少なくなる)
- 子宮内膜症の改善
- 卵巣がん・子宮体がん・大腸がんの発症リスクの軽減
- にきびの改善
生理痛を始めとした月経困難症や、子宮内膜症の改善目的で処方される場合は保険が適用される場合があります。
中用量ピル
中用量ピルは、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの配合量が、低用量ピルよりも多い薬です。
生理日の移動を目的として服用されます。
大事なスポーツの試合日や、旅行の日に生理が被りそうな場合などに使われるケースが多いでしょう。
すでに低用量ピルを服用している人は、休薬期間をコントロールすれば生理日を移動できるため、新たに中用量ピルを服用する必要はありません。
アフターピル(緊急避妊薬)
アフターピルは、避妊に失敗した場合や、普段飲んでいる低用量ピルを飲み忘れた場合などに避妊目的で服用する薬です。
性行為があってから72時間以内に服用します。
確実に避妊できるわけではなく、あくまで緊急時に使用する薬であるため、性行為の後に毎回服用すべき薬ではありません。
パートナーとの性行為で確実に避妊する場合は、低用量ピルが選択されます。
ピルの価格相場
ピルの種類や処方目的、処方を受ける医療機関によって値段は変わります。
ここでは、保険診療と自由診療の2つの場合に分けて、ピルの費用を解説します。
保険診療の場合
月経困難症や子宮内膜症と診断された場合、保険適用で3割負担となります。
薬によって値段が異なり、1シート(28日分)あたりの値段相場は1,000~3,000円程度です。
同じ薬であれば、どのクリニックでも値段は同じです。
薬代のほか、診察料や処方料がかかります。
自由診療の場合
生理日の移動や、避妊を目的にピルを服用する場合は、全額自費となります。
値段相場は以下のとおりです。
| 低用量ピル(1シート28日分) | 3,000円~10,000円程度 |
| 中用量ピル(1シート21錠分) | 5,000円程度 |
| アフターピル(1回分) | 8,000円~10,000円程度 |
クリニックや薬の種類によって費用は異なります。
診察料が別途かかる場合や、オンライン診療の場合は送料がかかるケースもあります。
低用量ピルを服用する場合は定期的に受診が必要なため、診察料や送料を含めた費用を確認しておくと継続しやすいでしょう。
ピルを飲む際の注意点5つ
ピルを飲む際の注意点として、以下の5つがあります。
それぞれの注意点について、くわしくみていきましょう。
血栓症のリスクがある
ピルの最大のリスクとして、血栓症があります。
血栓症は、血のかたまりができて血管がつまってしまう病気です。
年間で血栓症が起こる人の割合は、以下のように報告されています。
| ピルを服用していない人 | 1万人中1~5人 |
| 低用量ピルを服用している人 | 1万人中3~9人 |
| 妊娠中の女性 | 1万人中5~20人 |
ピルを服用している人は、妊娠中の人よりも血栓症のリスクは低いとされていますが、普段と違う症状に注意が必要です。
血栓症は、ピルを飲み始めてから4ヶ月以内に起こるケースが多いとされています。
以下の症状があれば服用を中止し、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 激しい腹痛や頭痛
- 胸の痛みや、息苦しさ
- ふくらはぎの痛みや赤み
- 意識の混濁
- 見づらさ、喋りづらさ
医師の診断により血栓症のリスクが高くない場合は、体調に注意すれば服用を恐れる必要はありません。
副作用が現れる可能性がある
ピルには、血栓症以外にも不正出血や吐き気などの副作用が現れる可能性があります。
よくみられる副作用は、以下のとおりです。
- 不正出血
- 吐き気
- 頭痛
- 乳房の張り、痛み
- むくみ
ただし、3シート(3ヶ月)程度服用すれば、症状が落ち着くケースが多いとされています。症状が強い場合や、3シート服用しても改善しない場合は、ピルの種類を変えると改善する場合もあります。
症状が辛い場合は、ピルの服用を諦めずに医師に相談することが大切です。
服用できない人もいる
先に説明したように、ピルには血栓症のリスクがある薬です。
これまでにかかった病気や、現在の健康状態によっては、血栓症のリスクが大きくピルが処方できないケースもあります。
リスクが高いといわれるケースの例は、以下のとおりです。
- 前兆を伴う片頭痛がある
- 高血圧である
- 年齢が40歳以上である
- 過去に血栓症に関連する病気にかかった
- タバコを吸っている
ピルを服用できない場合「生理痛には痛み止めを服用する」「避妊目的ならコンドームを使う」など、ほかの方法での対応が必要です。
低用量ピルは毎日決まった時間に飲む必要がある
低用量ピルは、女性ホルモンを体に取り入れて排卵を防ぐ薬です。
服用時間が毎日バラバラだったり、飲み忘れる日が続いたりすると、ホルモンバランスが崩れて避妊や生理痛改善などの効果が薄れる恐れがあります。
ピルの服用時間帯は、特に決められていません。
1日の中で自分が最も忘れにくい時間を設定し、アラームをセットするなど飲み忘れないよう工夫しましょう。
性感染症を防ぐにはコンドームが必要である
性感染症を防ぐには、性行為の最初から最後まで、コンドームを正しく使用することが必要です。
ピルには性感染症を予防する効果はありません。
性感染症とは、性行為によって感染する病気の総称です。
口や皮膚にある傷、性器から侵入するウイルスや細菌によって感染します。
性感染症にはクラミジアやHIV感染症、梅毒など、症状が現れるまでの期間が長い病気もあり、気づかぬうちに感染しているケースもあるのです。
性感染症になると、かゆみや痛みなどの症状だけでなく、病気によっては不妊や後遺症の原因になる場合もあります。
一度感染すると、正しい治療を受けなければ治らないため、不安のある場合は早めに検査を受けましょう。
DMMオンラインクリニックはオンライン診療でピルの処方を受けられる
DMMオンラインクリニックはビデオ通話でピルの処方を受けられるオンライン診療サービスです。低用量ピルはもちろん、中用量ピルやアフターピルにも対応しています。
またDMMオンラインクリニックでは、スキンケアや花粉症、メディカルダイエットなど、ピル以外の診察も可能です。
DMMオンラインクリニックを利用すれば、忙しいときでも病院へ直接足を運ばずにさまざまな健康上の悩みを解決できます。
ピルは正しく飲めば何歳からでも服用可能!
ピルは、生理が始まってから、40歳頃までの間であれば何歳からでも服用できる薬です。
避妊効果のほか、月経周期を整えたり生理痛を和らげたりする効果が期待できます。
ただし、ピルには血栓症のリスクがあるため、婦人科やオンライン診療で医師の判断のもと、正しく服用することが大切です。
オンライン診療であれば、自宅にいながら気軽に診察を受けられて自宅にピルが届きます。
婦人科の診察に「なんとなく行きにくい」「忙しくて行けない」と感じている方は、気軽にオンラインで診察を受けてみてください。
ピルの服用年齢に関するよくある質問
ピルの服用年齢に関するよくある質問をまとめました。
ピルを飲むとどれくらいで避妊効果が得られる?
生理が始まってから5日目以内にピルを飲み始めた場合、継続して服用していればすぐに避妊効果が期待できます。
ただし、6日目以降にピルを飲み始めた場合、7日間連続してピルを服用するまでは、確実に避妊できるとは言えません。
コンドームを使用する、性行為を控えるなど、ほかの避妊方法を併用する必要があります。
いつ飲み始めるかによって効果のタイミングが変わるため、診察の際に服用開始のタイミングを確認しておくと安心です。
ピルを服用しても将来妊娠できる?
ピルを服用しても、不妊の原因にはなりません。
ピルを飲むのをやめると排卵するため、妊娠する可能性があります。
海外で行われた研究によると、避妊を中止後1年間の妊娠率は80%を超えており、ピルの服用は妊娠に影響を与えないと報告されています。
ピルを飲むと太る?
「ピルを飲むと太る」との噂を聞いたことがある人もいるかもしれません。
実際には、体重増加にピルは関係ないと証明されています。
服用し始めて太ったと感じる主な原因は、むくみや食欲増進です。
ピルの成分であるプロゲステロンには、体内に水分を溜め込む作用や、食欲を増進させる効果があります。
ただし、むくみや食欲増進の副作用は、3ヶ月程度服用すると落ち着くケースが多いとされています。
ピルの服用にかかわらず、規則正しい生活や栄養バランスの整った食事を心がけることが大切です。
【参考文献】
[1] 日本産婦人科学会編「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」
http://www.jsognh.jp/common/files/society/guide_line.pdf
[2] 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会「産婦人科診療ガイドラインー婦人科外来編2023」
[3] 厚生労働省「性感染症」
[4] Tadele Girum,Abebaw Wasie.Return of fertility after discontinuation of contraception: a systematic review and meta-analysis.Contracept Reprod Medicine.2018

[5] 働く女性の心とからだの応援サイト「女性は一生にわたって女性ホルモンに影響を受ける?! 」